HP 「AzPainter2を使おう」「AzPainter使い倒し」の連動ブログです
「AzPainter使い倒し」で紹介した花火の画像を背景にして、別レイヤで猫を描き加えただけのイラストです。
ゼロから全て描くのは面倒でも、背景は「作って」いるので、随分ラクに仕上げられますね。
なお花火をたくさん打ち上げた画像にする時は、大きく開いた花火を上に、小さいものは下に配置すると、それっぽく見えます。
(実際、大きな花火ほど上空まで上がってから炸裂するので)
PR
北京オリンピックのテレビ中継を見ていたら、競泳などが行われている国家水泳センター(Watercube~水立方)の外壁が、とても個性的で印象に残りました。
この外壁の独特の模様(と言うか、壁面の分割方法)は、おそらくAzPainterの「水晶」フィルタと同じです。
そこでAzPainterを使って、CG的にこの外壁を模した画像を作ってみました。

どうでしょうか・・・? (^-^;)
向こう側が透けて見えたり、光が差し込んでいる様子も表現しました。
国家水泳センターの外壁は、夜間ライトアップされると青く見えますが、日中はこんな感じですよね。
この平面分割は、純粋な数値計算でできていますが(そうでなければコンピューターで生成できない)、どこか有機的な雰囲気があって、好きな模様の1つです。
この外壁の独特の模様(と言うか、壁面の分割方法)は、おそらくAzPainterの「水晶」フィルタと同じです。
そこでAzPainterを使って、CG的にこの外壁を模した画像を作ってみました。
どうでしょうか・・・? (^-^;)
向こう側が透けて見えたり、光が差し込んでいる様子も表現しました。
国家水泳センターの外壁は、夜間ライトアップされると青く見えますが、日中はこんな感じですよね。
この平面分割は、純粋な数値計算でできていますが(そうでなければコンピューターで生成できない)、どこか有機的な雰囲気があって、好きな模様の1つです。
AzPainterには「通常」も含めれば、15のレイヤの合成モードがあります。
このそれぞれがどう違うのか、どう使い分けるのか、そもそも一体どういう用途に使うのか・・・疑問に思っている方も多いと思います。
結論から言えば、実際に使ってみて経験的に身に付ける他はないのですが、その取っ掛かりの1つとして「中性色」から攻めてみる?方法を紹介します。
まず、適当な画像を用意します。
今回は↓↓↓の、花の写真を使ってみました。

次にこの画像の上に新規レイヤを作って、黒・50%灰色・白の三色で塗りつぶします。
なお50%灰色とは、RGBカラーで(128、128、128)のことです。
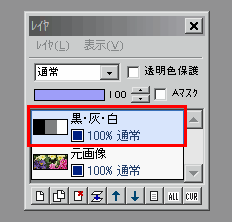
この「黒・灰・白」レイヤの合成モードを順に切り替えて、合成結果がどうなるか見てみましょう。
この時、元画像に影響を与えない色が、その合成モードの「中性色」ということになります。
「乗算」です。 ↓↓↓ 中性色は白です。

「スクリーン」です。 ↓↓↓ 中性色は黒です。

「ハードライト」です。 ↓↓↓ 中性色は50%灰です。
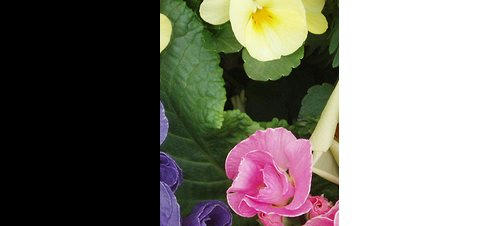
他の合成モードも全て試してみると・・・・中性色が
白・・・乗算、焼き込み、焼き込みリニア
灰・・・オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、ビビットライト、リニアライト、ピンライト
黒・・・加算、減算、スクリーン、覆い焼き、差の絶対値
となります。
上のレイヤで中性色の部分は、下のレイヤに対して「透明」になると考えてもいいでしょう。
こういうことを利用して、二つの画像の必要な部分を上手く合成して目的の結果を出すのです。
この実験では同時に、「乗算⇒黒は完全に下のレイヤを覆い隠す」などもわかります。
皆さんも色々な画像で試してみてください。
「AzPainter使い倒し」のこちら↓↓↓の記事もご参考に
レイヤの合成モード豆知識
このそれぞれがどう違うのか、どう使い分けるのか、そもそも一体どういう用途に使うのか・・・疑問に思っている方も多いと思います。
結論から言えば、実際に使ってみて経験的に身に付ける他はないのですが、その取っ掛かりの1つとして「中性色」から攻めてみる?方法を紹介します。
まず、適当な画像を用意します。
今回は↓↓↓の、花の写真を使ってみました。
次にこの画像の上に新規レイヤを作って、黒・50%灰色・白の三色で塗りつぶします。
なお50%灰色とは、RGBカラーで(128、128、128)のことです。
この「黒・灰・白」レイヤの合成モードを順に切り替えて、合成結果がどうなるか見てみましょう。
この時、元画像に影響を与えない色が、その合成モードの「中性色」ということになります。
「乗算」です。 ↓↓↓ 中性色は白です。
「スクリーン」です。 ↓↓↓ 中性色は黒です。
「ハードライト」です。 ↓↓↓ 中性色は50%灰です。
他の合成モードも全て試してみると・・・・中性色が
白・・・乗算、焼き込み、焼き込みリニア
灰・・・オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、ビビットライト、リニアライト、ピンライト
黒・・・加算、減算、スクリーン、覆い焼き、差の絶対値
となります。
上のレイヤで中性色の部分は、下のレイヤに対して「透明」になると考えてもいいでしょう。
こういうことを利用して、二つの画像の必要な部分を上手く合成して目的の結果を出すのです。
この実験では同時に、「乗算⇒黒は完全に下のレイヤを覆い隠す」などもわかります。
皆さんも色々な画像で試してみてください。
「AzPainter使い倒し」のこちら↓↓↓の記事もご参考に
レイヤの合成モード豆知識
道路に落ちている猫の影が面白いと思い、撮った写真です。
しかし全体にコントラストが甘く、目で見た時と比べて平凡な写真になってしまいました。
これをレタッチしたのが次の写真です。
影が強調されて、イメージ通りの写真になりました。
元画像の上に新規レイヤを作り、白⇒黒のグラデーションを描画してから、レイヤの合成モードを「オーバーレイ」にしただけです。 ↓↓↓
簡単なレタッチですが、効果バツグンですね。
AzPainterでは、直線・円形・矩形など色々な形のグラデーションが描けるので、陰影をつけたい場所に合わせてグラデーションを描きます。
レイヤの不透明度を下げると、効果の強さが調整できます。
また「ソフトライト」にすると、「オーバーレイ」よりも効果が柔らかくなります。
好みで使い分けるといいでしょう。
写真を撮る方は皆さん気づいているでしょうが、カメラにはなかなか目で直接見た印象と同じには写ってくれません。
後で写真を見てみたら「こんなはずじゃなかった・・・」と思うことは良くありますね。
そんな時は、レタッチで何とかできないか考えてみましょう。
撮影した時のイメージを、写真を見る人にも上手く伝えるために、レタッチはあるのです。
このレタッチの詳しい説明はこちら↓↓↓
「オーバーレイ」で陰影を強調
カテゴリー
スポンサードリンク
スポンサードリンク
Twitterやってます
HP の掲示板情報
ブログ内検索
過去の記事

